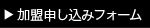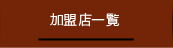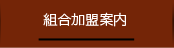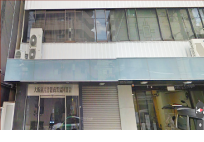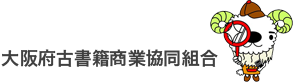読むよりも買うのが楽しい古本道
ぼくはこれまでに古本についての本を四冊(うち一冊は文庫)、文庫についての本を二冊書いている。編集・執筆としてかかわった 『ニッポン文庫大全』という大著もある。古本についての原稿依頼もけっこう多い。京都で大学生活を送っているころ、毎日のように京都、大阪の古本屋を行脚したが、まさか将来、古本のことで文章を書いて食べていけるなんて思っていなかった。今思うと、ありがたいような不思議なような気分だ。
一年三六五日、古本のことを考えない日は一日たりともない。夢にだってよく見る。夢の中に自分が作り上げた古本屋街があって、くりかえしその街が出てくるのだ。たいてい、自分が欲しい本が並んでいて、それも安い値段がついていて、ほくほくと選んでいるうちに目がさめる。いずれにしても、重症の古本病患者であることは間違いない。
そんなぼくが、普段どういう古本の買い方をしているか、を書いてみたい。そのなかに、売る側として何か商売のヒントになるようなことを拾い上げてもらえればいい、と思う。断っておくが、ぼくはミステリやSF、マンガなどの収集家ではなく、初版本、稀観本のマニアでもない。「均一小僧」というあだ名までもらっている通り、もっぱら、五百円以下の安い本ばかりを漁っている。古本屋さんにとっては、上得意とはいいがたい。すびばせんね。
そこで、最近買った中から、めぼしい本をいくつか紹介していくことで、ぼくの古本の買い方を察していただくことにしよう。十一月三十日には高円寺古書会館の即売会で六冊ばかり買っている。一番の買い物は、生方敏郎『食後食談』(昭和3年・萬里閣書房)で、千五百円。この値は、ぼくとしては思い切った方だ。裸本で傷あり、だからこの値段で、箱入りだと五千円はするだろう。生方の説明は釈迦に説法ではぶくとして、目次をざっと見て、「初めて自動車に乗るの記」 「モダーンガールのこと」「女の反逆は甘やかすもとだ」「サラリーマンの浮き沈み」なんてタイトルが引っ掛かってきた。
ぼくはここ数年、関東大震災後から昭和の初年あたりまでの、都会の世相風俗を扱ったものに興味を持っている。昭和初年の発行というだけで、『玉突き術』『社交ダンス』 『犬の飼い方』なんて本を買うことがある。
『模範綴方全集 五年生』(昭和14年・中央公論社) も同様のライン。箱入りのモダンなデザインが気に入ったということもあるが、中を開いて最初の奈良県三島小学校の中西俊一くんの文章「僕の家は一昨年まで玉突の店をしてをられたが、姉ちゃんが東京へ帰ってからは、ゲーム取りをする人もいないし(後略)」を読んで、これは買いだと決めた。値段は五百円。高峰秀子が豊田正子に扮した『綴方教室』という映画を観たばかりであったことも影響している。綴方運動そのものにも興味があるのだ。
『ふらんす』 の臨時増刊「しのび笑い」(昭和32年・白水社)は百円。これはフランス艶笑小咄を原文と訳文、それにイラストで構成した雑誌。このイラストがいい。雑誌の場合は、目についた時、引かれるものがあったら買っておかないと、なかなか次が見つけにくい。 朝吹登水子『私の巴里・パリジェンヌ』(昭和52年・文化出版局)と、『土屋耕一のガラクタ箱』(昭和50年・誠文堂新光社)がともに二百円。これは、両方とも持っている可能性が高いが、押さえで買っておくかという感じ。ぼくはときとして、すでに持っている本を買うことがある。文庫の場合はそれが顕著で、海野弘の 『モダン都市東京』(中公文庫)などは五冊も持っている。
この「同じ本を意識して複数買う」という性癖が、古本菌に感染していない一般人にはどうにもわからないらしい。そのことを話すと、たいてい「なんで?」と不審な顔をされる。しかし、ぼくのまわりの古本仲間はたいていこれをやっている。
もちろん、絶版本で、値段が安いことに限られるが、自分が好きで、しかも容易には手に入らない本が、安いまま誰にも買われず放置されてあると、放っておけないという気持ちが働くのだ。雨に濡れた小犬が、露地の奥で震えながらクンクン泣いている、という感じだろうか。おお、よしよしと胸に抱き上げてしまう。もちろん、余分に買った本は、それを欲しがっているしかるべき人にあげてしまう。古本を有効に生かそうといいう殊勝な気持ちも持っている。
高円寺古書即売会の前日、二十九日には五反田古書会館の即売会を覗いている。ここは、一階会場がほとんど雑本雑誌の処分市となる。二百円三百円でそれなりにいい本が買えるので、開場の九時半をなるべく遅れず馳せ参じるようにしてる。均一小僧のぼくとしては、山奥の秘湯みたいなもので、本当なら独りで浸かりたい。筑摩の明治大正図誌の『京都』『近畿』を各二百円で買った。千円以下で買えるのは稀れだ。これで、全十七巻のうち、いずれも古本で五冊が集まった。なんとかバラで全巻をあわてず騒がず収集したい。
窪鴻一・三室葉介『猟奇の都「巴里・東京」』 (昭和5年・正和堂) 五百円も、胸の中で!マークが三、四個点滅、値段を確認して脇に抱え込んだ。背が取れて、大きく補修した後に、マジックでタイトルが書き込まれてある。状態はかなり悪いが、ぼくの場合はあんまり気にしない。とりあえず、読めればいいのだ。挿絵がたくさん入っていて、小出楢重の装丁であることもポイントは高い。
それにこの本、著者は両名とも知らない人だったが、巴里本であることと、戦前の海外渡航記、とぼくの収集ジャンルのうち二つをカバーしている。知らない著者の本を買いはじめると、古本道でも、かなりぬかるみに足を踏み入れたことになる。少なくとも、学生時代には、未知の著者の本を買うことはなかったもの。しかし、自分の関心を惹いた本、というものさしで選ばれた本なら、ある程度集まってくると、自然に道筋というか体系ができあがってきて、著者のこともわかってくる。このあたりが、古本ならではの楽しさ、旨味だろう。
ほかに、植草甚一スクラップブック16 『映画はどんどん新しくなってゆく』(昭和52年・晶文社) が六百円で出ていたので買った。まさしく、これなどリアルタイムで学生時代に買っていた本。このところ、値が上がりつつあるものの一つ。これも言うまでもないだろう。巻によっても違うが、だいたい千五百円くらいついている。なんといっても、植草甚一がぼくらの世代に与 えた影響は大きい。「古本屋めぐり」 につきまとう、それまでのじじむさいイメージを、植草さんはカジュアルかつポップなものに変えてしまった。
学生時代に集めていて、その後手放してしまい、いまになって買い直している本、というのもたくさんある。ぼくにとって今年は、リチャード・ブローティガンがマイ・ブーム。ほとんどの邦訳を担当した藤本和子さんによる評伝が出たことで、急に読み返したくなって古本屋を駆けずり回るが、まるでそんな作家などいなかったように棚から消えていた。ほんの十年ほど前まで、均一台にでも転がっていたような気がしていただけに、狐につままれたような思いだった。
しかし、ない…となると古本魂が燃える。この飢餓感を、古本屋さん側から仕掛けるのは難しいと思うが、新刊書店の売り場をこまめにリサーチするぐらいのことは必要ではないだろうか。今年、話題になったマンガに高野文子『黄色い本』(講談社) を御存じですか。マンガという表現が、いったいこんなところまで来ていいのか、と恐れる程素晴らしい本だったが、この表題作全編にわたって、じつに魅力的にロジェ・マルタン・デュ・カール 『チボー家の人々』が引用されている。『黄色い本』を読んだ人が百人いれば、八十七人までが必ず『チポー家の人々』を読みたくなる、というマンガだが、全国の古本屋さんで、この『黄色い本』 に連動させて、倉庫から 『チボー家の人々』を引っ張り出してきた人がいったい何人いるだろうか。
ぼくは、小津安二郎の映画『麦秋』 の中で、二本柳寛と原節子が北鎌倉の駅ホームで、やはり『チボー家の人々』 についてやりとりするシーンがあり、それを観て、あわてて古本屋に『チボー家の人々』を買いに走った覚えがある。結局、読まずに売ってしまったが・・・。この場合は読む必要などない。欲しいと思い、たまらず古本屋に駆け込んで手に入れる。その行為の中に、すでに古本の代金分は解消されている。買った古本をすべて読もうなんて、了見が太いというものだ。
五反田ではほかに、「明星」臨時増刊『グループ・サウンズがやってさた』(昭和43年・集英社) を千円で買っている。ギリシア神話に出てくるアポロンのょうな、美しいジュリー(わし、ホモと違いまっせ) が表紙だ。一過性の流行りもの企画ながら、編集やデザインが凝っていて、その意味でも貴重な時代の証言を果している。
とりとめなく書いてきたが、これが「私の生きる道」 であります。しかし、これでも十月末に引越しがあったせいで、ここ数ヵ月は買い控えているほうだ。なんたって、古本は読むより買うのが楽しい。どうか古本屋さんは、こんな古本バカめがけて、なるべくツブシにせず、いろんな本を店頭で、即売会で、デパート市で怒濤のごとく放出してください。